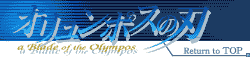シーン4-3:
「だからなぁ、ウチにゆーたって何にも解決にならんちゅーねん」海藤瑠璃の狭い部屋の中では、まだ六人がいた。
いや、もう一人。
学校の研究室でこの事を知り、ここならばと駆けつけた矢川谷保が来て七人にふくれあがっている。
「でも相手はガイアの声なんでしょ?」
「あのなぁ、ガイアの声っていっても60も70もある環境団体の集合体なんや。その一個一個なんか覚えてられるかい」
ガイアの声は2023年に設立となっているが、元になった組織は二十世紀後期のアメリカ在住の主婦達の集まりだった。
それが長い活動の中、他の環境団体との合併・吸収・分派を繰り返し。ガイアの声の元となった組織、ガイアの囁きの系列団体だけで世界各国150を越える団体が存在していた事になる。そしてある人物の提唱により、120団体が同調し世界最大の環境団体『ガイアの声』が出来上がった。しかし今ではあまりにも巨大な為に分派が派生し、その根幹は同じであるが瑠璃の言うとおり現代の状況と協調しながら活動を行っていく穏健派と、過激な方法でその活動を行う過激派もまたいる。そしてその穏健派と過激派はお互いに相容れないことを知っているのだ、もし連中が穏健派であるなら(この様な事態を起こして穏健派である可能性はないのだが)、同じ穏健派である瑠璃に一報が入っても良いはずだ。しかしそれをしていないと言うのは、この事件の規模や非人道的なやりくちから見て過激派に分類されるべきの者達だろう。
「でも、瑠璃さんはここの統括なんでしょ?」
「せや」
「だったらだよ、そこの元締めの許可なしに何か行動なんかできるの? できちゃったとしたら組織として問題ない??」
谷保の質問は理にかなっている。
「元締めって、ヤクザやあるまいし。でも、まぁ活動がガチコらんように連絡はあるはずなんだけどな」
「じゃあ、そこに連絡がきてるかもですわね」
「あすこに電話すんのいやなんやけど」
「少なくとも今、行動はすでに起きていてこうやってる合間にもどんどんトライデントがバラバラになっていきますわ。このままでは学校も……」
ガコーン!
激しい音が響き渡る。
「どうやら」
「ええ、モノレールの駅が一つ倒壊してるみたいですわね」
「でも、みんな何か落ち着いちゃってるね」
街の人たちがみな港へと殺到しているのに対し。
危機意識が無いわけではない、が。
「港に行っても船があるとは到底思えないしな」
「ええ、テレビでの報道では12時間なんて言っておきながら、もうすでに行動が起きていること考えれば」
「この島の人間全員を海の底に突き落とそうって算段だろ」
逃げ場がないならオタオタしたところでどうにもならない。
だからこそ、この部屋にいる人間は落ち着いていられるのだ。
逃げてダメなら、原因を排除する。
という話をしたとき、一人だけ智己が取り乱したがしばらく大騒ぎして意識はどっかに飛んでいた。
その為にここにあつまっているのだが、肝心の瑠璃が動こうとしない。
「何が気になるの、海藤さんは」
「なんかな、うちはコレが何かの意味があるんやないかと思ってしゃあないんや」
「意味? ここを壊すことでしょう?」
「いや、それがな手段やったらどうなんかなぁと」
どんな手段があるというのか。
「いや、わからへんねん。なんというか勘でしかないんやけどな」
瑠璃はため息をついた。
「確かにトライデントをバラバラにしてしまうのは、タダでさえも先の事件で有名どころか世界中から注目されているトライデントUNですもの、世界中がその様子をみますわね。もし私が犯人なら今すぐに壊さず、この島の人間全員を人質にしますけどね」
皐月の物腰の柔らかさと、その発言の内容とのギャップが面白い。
そうなのだ、自分の要求を通すだけなら人質をとって、アジテーションすればいい。それが賛同されるかどうかは判らないが、メッセージは世界中にニュースという形で流れるのだ。
「そもそも犯人はどこからコレやってるんでしょうね?」
「多分、ネプチューンからでしょ」
「矢川さん知ってるの?」
「今つきあってる男が、技術者でトラコに入ってる」
「あ、でもネプチューンってなんですか?」
「みゃーこ、知ってるよ。トライデントUN全体を管理してるホストコンピューターだよねっ」
「美也子さん正解」
「ってことはだよ、誰かがそのネプチューンとかやらを直接コントロールしてるってこと?」
「直接ってことは、トラコの中にその仲間がいるの?」
「確かめてみよう」
谷保がビジフォンを出すと、その谷保の男へ連絡をつけている。
その話している横で智己が台所へ消えていった、まだ目は死んでいるようだが。
「どうやら内部じゃないってさ」
「こんな時でも情報が外に漏れてしまうなんて」
「あちらさんも混乱しまくってるってことじゃないの、まぁこれで少しは犯人に近づけたってことでさ」
しぶきが智己の煎れてくれた茶を飲む。
とはいえ、一人暮らしの家に湯飲みが有るわけではないから、茶碗やらお椀やらに煎れられてきていた。
「でも外部からとなるとやっかいだね」
「世界中からアクセスはできますから」
「こういうときは犯人の気持ちになるのが大切ですよね」
そう簡単に犯人の気持ちになれるわけではない、が。
「ま、とりあえずここだとそのまま沈没しそうだし」
「そうですね、12時間経つよりも前に海底に部屋は沈んでしまいそうです」
「え、助かる場所があるの?」
智己の目が輝く。
「場所があるもなにも……」
「切り離されない場所にいけばいいだけじゃない」
「うん、支柱のあるブロックとかに」
散々なツッコミを入れられる智己がいた。
「そんな、気づかなかったの私だけ……?」
「大学の小型艇で海にいくのもありだとみゃーこは思う」
シーン1-3:
海凰の上では救助艇を取り囲み様々な検査が行われていた。「爆発物らしきものを積み込んでいるのは確かです」
一人の技術者がエコーの機械を見つめながら呟く。
「集音マイクで電気音を確認しました」
次々とくる報告は、それが爆弾を積んだ救助艇であることを可能性づけるものばかりである。
「こんな所で解体という訳にもいかんか」
ブリッジから降りてきた太平洋は、つり上げられた救助艇を見に来ていた。
その丁度三角形のテントのような救助艇は、全面が黄色のビニールで出来ていている。一昔前の救助艇のような感じだ。
「はて、どうしたもんか」
太平洋が腕組みをしながら考えていたときだ。
「すてちゃえば?」
鈴が笑顔で太平洋の後ろから答える。
海凰が少しうなりを上げて前進する、潮の流れで動いた分を調整しているのだ。
「捨てると言ってもな、どんな爆弾かもわからんのにほいそれと捨てるわけにも」
「ボクが思うに、時限爆弾なら海凰が上手くこの地点にこないといけませんよね?」
「うむ」
「光反応だとしたら、黄色いテントはだめですよね?」
「うむ」
「中にジャイロとかあって、動かしたらドカンなんていうのは波があるんですから論外ですよね?」
「ふむ」
「音反応も論外ですしだとしたら、あの中に入って爆弾確認しても大丈夫だと思うんです」
「しかし、あの中に入ると言っても」
「身体がちっちゃければ大丈夫だとおもいますよ」
「いや……」
太平洋は鈴の方を向いた、その後ろには工具箱をもった雅美の姿もある。
「……しかし」
「まだまだ死ぬ気はありません、ジェレミー先生が守ったこの船を、今度はボクが守る番なんです」
太平洋は押し切られる形でそれを認めた。
「鈴ちゃん、そっちどう?」
「ビス穴は全部溶接されてる」
「時計音はないよね、デジタルだったらおしまいだけど」
「それもなさげ」
救助艇の中には確かに黒い箱が一つ置いてあった。
鈴と雅美はそれを中心ににらめっこするような形でうつぶせになっている。
中での会話は外にいる人間にも聞こえるようになっている。
「じゃあ、開けてみようか」
「そうですね」
『待て!!』
ビス穴を溶接したハンダを溶かし開けようという作業の手前で、その声がかかった。
救助艇の外、その声の主は世良でも太平洋でもない、一人の技術者だった。
「何を言っているんだ貴様」
その技術者は右手に黒い物を持っている。
「これはその爆弾の起爆スイッチだ、それ以上その爆弾に触れるとスイッチを押すぞ」
「要求はなんだ?」
太平洋が大声で怒鳴る。
「我らガイアの声の為に、悪しき科学の船は海底へと沈んで貰う」
『じゃあ、何で今まで押さなかったの?』
インカムから来たのは雅美の声。
「や、やかましい」
『鈴ちゃん、解体しよ』
「ダメだ、それに触ると爆破するぞ!」
『すれば? 待っていてもどうせ死んじゃう、解体しても死んじゃう。なら生きるために解体する方を選ぶわ』
「いいのか、お前の勝手な行動で今すぐお前達、海凰の全員が死ぬんだぞ!」
『キミ、いってることが変だね』
鈴の声。
『この船を沈めるだけなら、へんな脅迫状なんかいらないよね。この船をつり上げたときにドッカーンってやっちゃえばいいんだから。じゃあ、なんで脅迫状なんか書いてあったのか』
シュッというハンダの溶ける音がインカムから響く。
『元々、脅迫状なんてなかったのよ』
『うん、本当はとっとと爆破するつもりだった、多分それが計画』
『だけど、それをやる人間がちょっとだけ臆病になった』
『多分、海底内のブイっていうのは偽物よね』
ガコッとふたが開けられる音。
『その脅迫状を見つけた技術者と、今しゃべってる技術者って同じ人じゃない?』
「……そうだ」
太平洋はボソリと呟いた。
『臆病になって、死ぬのは嫌だけど計画は遂行しなきゃいけない』
『だから予定を変更した、爆破するんじゃなくて足止めをする』
『もし、トライデントUNで仲間が失敗しても一応自分は生き残れるしね』
『だからあなたはそのスイッチを押さない』
『私たちが解体してしまったら、言い訳もできるしね』
『じゃ、これで爆弾は不発弾っと』
インカムからパチリという電線を切る音が響く。
「ってわけで、その役立たないスイッチはこっちに渡して貰うぜ」
世良が技術者に近づき、スイッチを受け取った。
技術者は屈強な乗船員に連れられて、個室へと運ばれる。
「こっちはいいよ、雅美ちゃん鈴ちゃん」
世良の声かけに。
『あ、おっけー』
『やれやれ』
鈴と雅美が救命艇から降りてくる。
「解体した爆弾はどこだね、まだ救命艇の中なのか?」
「へ?」
「ボク達、解体なんかしてないよ?」
太平洋が絶句する。
「爆弾の解体なんか経験ないもの、下手にいじったらドッカーンってなっちゃうかもしれないし」
「そうだよね」
鈴と雅美が向き合って笑顔になる。
「じゃあ、今までのは全部」
「ぜ〜んぶお芝居」
なんてこったと太平洋はつぶやき、顔を覆った。
「まったく、この娘達はなんなんだ」
世良にも鈴達のねらいは判っていた。それ故にとっとと技術者から爆破スイッチを取り上げることが出来た訳だ。
「特別製なんですよ、きっとあの世代は」
呆れる太平洋に世良は、そう答えた。
シーン8-3:
ネプチューンにいた科学者達は、その光景を目にした。次々とパージされていくブロック、しかし注目はそっちではない。
「なんだ、この乱数は」
「おい、これはどこに接続してるんだ?」
「判りません、いま確認してます」
今、画面上では恐ろしいまでの早さでアルファベットや数字が流れ、次々と桁を確定していく。
すでに二千以上の数字が並んだ。
「判りました、米軍のミサイル発射基地です」
場所は変わって洋上。
「やつらようやく気づいたようだね」
「もう、手遅れですけど」
小型艇の中でノート型パソコンの中で、次々とミサイル基地のパスコードを確定させていく。
「まさか、奴らも世界最速のホストコンピューターでハッキングされるなんて思ってもいないでしょうね」
彼らの乗った小型艇からは海中に一本のケーブルがのびている。
トライデントに張り巡らされた網の一本であり、中途介入のためどこの端末とも確定できない盲点をついていた。
「これで我々の悲願が達成される、人間も科学も無い地球をつくることが出来る」
ネプチューン内では、その恐るべき計画がようやく解明された。
「このパスコードはソニックバンカーのコードです」
ソニックバンカーは、爆裂すると超音波が四散し水分揺さぶる兵器である。水分が少ない物にはほぼ無害であるが、大量の水分を持ったもの、たとえば人間がこの影響をうけると、あっという間に体温が六十度を超え身体のタンパク質をすべて変成させて死に至る。海も一時的に六十度となるが、局地的な温度変化は海全体から見ればなんら問題はない。植物にしてもだ。建物もほぼ無傷で残ることから環境に優しい殺戮兵器と呼ばれている。
「USから抗議が来てます!」
「馬鹿野郎、それどころじゃねえって言って置け!」
「パスコード全部解明まであと二十分をきりました」
「場所はどこだ、どこに着弾する」
「一つはトライデントUN、もう一つは……」
「石油成金どものど真ん中か」
「アメリカのミサイル発射場、くそっ!」
場を仕切っていた男がインカムを床に投げつけたときだ。
「最悪です、この表示もダミーです。いえ本物ですが、この裏でアメリカ二十六ヶ所のミサイル発射場にハッキングしてます」
場を仕切っていた男は再び自分のこめかみ辺りを手探ったが、投げつけるインカムはすでに床に転がっていた。
その頃、小型艇内部では大詰めを迎えていた。
再び演説が始まった。
『この放送を聞くすべての人間へ、これは地球の意志であり我々はその代弁者である。地球にいる人類は肥大し、明らかに地球が自浄作用で支えるにはあまりにも大きすぎるほどの害虫となった、よって我々人類は滅びなければならない。再び地球を我々人間の居ない原始に返し、我々の行った無知な地球への大いなる貸しを自ら滅することで返さなければならない!』
男は小型艇の上に出て場所が特定されないように、背景を海だけの場所に選んでいた。
『我々はアメリカの持つ科学の生み出した悪魔の寵児ミサイルによって滅びる、我々の言葉が嘘ではない証拠に我々ガイアの声、ゼウスの牙はトライデントUNのホストコンピューターを乗っ取り、アメリカのミサイルのすべてを確保した、オリュンポスから放たれる刃、オリュンポスの刃によって大地は神々の怒りによって切り裂かれ、我々人類は今日、終わりを迎える。先ずは愚かな科学の島、トライデントUNと共に我々も先にこの地球から消え去ることで証明する……』
放送は世界に流れた。
世界各地はパニックになる。
その中で冷静にその様子を小型モニターで見ていた集団がいた。
あの部屋にいた七人だった。
「彼らの発言が本物なら場所は、トライデントの中ですね」
「ああ、しかも洋上だ」
「しかし洋上といっても、脱出しようと言う船がありますし」
「あれ?」
しぶきが声をあげる。
「あのさ、ちょっと巻き戻して」
「このくらい?」
「いや、もうちょっと前」
「ここ、ここ見て」
それは男が演説している途中の海面だった、背鰭がほんの少しだけ映っている。
「ちょっと拡大するわよ」
谷保が画像を自前の端末に読み込み、その部分を拡大した。
この背鰭がもし。
「やっぱりだ、海洋大学のカウボーイだわね。識別票は……ホーリット!」
「行くよ」
しぶきが立ち上がる。
「瀬名さん、どこいくの?」
美也子が尋ねると。
「今日のホーリットの巡回地域は海洋牧場の北側だからさ」
「そこにいる小型艇に、あいつらが居る可能性があるんですね」
「っていうか、カウボーイのスケジュール。もしかして全部覚えているとか」
「基本だよ基本」
「先ずは船を手配しないと」
「そんなんじゃ遅れちゃうよ」
「せやな、ここは少数精鋭でいこ」
小型艇では男達が最後にパンとワインを飲んでいた。
あと数分もすれば、世界各国に三百発のミサイルが飛来していく。
それは世界の人口過密地帯を狙い、世界の動脈を分断していく。もちろん生き残る人間は出てくるだろう、しかし機能を失った世界では、人々は退化をしなければならない。もしくは文明を維持することさえ困難な状況にまでなれば、彼らの目的は達成される。
「あとは、時間まで眠りながら待つか」
ノートパソコンでは次々とパスコードを解析した結果が報告されていく。
あと数分もしないうちにすべての防壁が解かれ、あたらしい世界がやってくる。自分の手でその世界をつくったという達成感は味わえないが、すべてをやり尽くした心地よさに彼らは浸っていた。
そう、あとはすべてを終わりにする、一押しだけでいい。
ピッ!
彼らにとっての福音が小型艇に響く。
すべてのパスコードが解除された音だった。
「おおいなるガイアの意志、オリュンポスの刃となりて世界に降り注ぐがいい!」
男がエンターキーに触れようとした瞬間だった。
「そうはいかないよ!」
海洋カウボーイ、GFの背中にのったしぶきが急潜行し、小型艇から伸びるラインを引きちぎる。
その弾みでノートパソコンは小型艇の壁に衝突し、ドアを突き破りそして海の中へ落ちていった。
「たった二、三人が世界を決めてどないするっていうんや、地球はあんたらの物でもある、せやけどなこの地球はこの地球っていう船に乗ってるみんなのものなんや」
海洋カウボーイの松本君の背中から、小型艇に乗り込んだ瑠璃は水中銃を男達に向けた。
「貴様、その髪の毛、その目。裏切り者の海藤だな」
その男の言葉に瑠璃はすこし表情をゆがめる。
「どうでもいいですけど、その手を動かせば容赦なく切り落としますよ」
銃を握ろうと腰に手を回した男に、ホーリットが船を飛び越える大ジャンプをした後、その背中から飛び降り小型艇に乗り込んだ浮月のワイヤーがめり込む。
「確かに、あんたらからみればウチは裏切りものかもな。でも、自分の意志を通すため、ガイアの声の為に何で赤ん坊からみんな死ななあかん? 確かに地球こんなにしてもうたんは、自分たち人間の積み重ねてきた地球への暴力、だけどな、それを死んで詫びようなんてそれは間違いなんや。人間は地球を壊すために産まれてきたわけやない。これから未来、地球は絶対に」
「なんで言い切れる、未来にはとかいいながら、自分たちだけに都合のいい環境をつくろうとする人間が!」
「うちにもわからへん、だけどウチにもあんたにも未来は見えない、だからもっと良くしたいとここに仲間が集まってるんや。ウチがあんたらと仲良うできんのはそういうこと。ガイアの声を抜けたのは、そこにおらんでもここにおれば、きっと良くできる。そういう仲間がぎょうさん見つかったから」
男達が黙り込んだ後、しぶきがビジフォンで谷保にその様子を伝えた。
「ああ、まーちゃん。私、谷保だけど……もう、こっちは終わったみたいだからそっちでコントロールできるとおもうよ。え、なんで知ってるって? (連絡したことも忘れてるな、まぁいっか)乙女の勘ってやつよ」
ネプチューン内部では、一切受け付けなかったコントロールが戻り、復旧作業が続いた。
ミサイル発射基地では緊急で中止命令を出し、一大事を免れた。
数日後。
パージされた各地区は徐々に元の位置に戻され、接続復旧作業が続いた。
前回の事件よりさらに大きなダメージを受けたトライデントUNは、完全復旧までにまだ数ヶ月を要すると言われている。
エピローグ1:
「あ、いやぁ」「こっちも大変だったみたいですね、クリスさん」
「ああそうだな、まぁなんとかなったみたいだね。毎度のことさ」
クリスが港で出迎えたのは、有明晴海と瀬戸内夏姫の二人だった。
本来ならもっと早く帰ってくる予定が、先だっての騒ぎで港が使えずに結局一週間延びてしまったのだ。
「しかし、大胆だな」
「そうですか? やっぱりおつきあいするからには本気でしないと」
晴海が夏姫に告白したのは、大騒ぎのある数日前。
そしたら夏姫は、軽い気持ちでつきあうことは出来ない。もし本気ならと、結婚を前提としたつきあいを要求し、晴海も夏姫の実家まで行って交際の挨拶というのをしてきたのだ。
「告白がプロポーズになってるとは日本とは奥が深い」
「そういうクリスさんも、変わりましたね」
「そうか?」
「前よりも、優しくなった気がします」
「そういわれると照れるな」
「クリス、お出迎え終わったらそのまま帰島婚前宴会だぞ!」
港の遠くから蓼島が手を振る、それに笑顔で手を振って答える。
「さぁ、お前達のための宴会だ。明日の朝日を拝むまで飲ませるからな」
「ちょ、ちょっと僕たちは長旅で〜」
焦る晴海をよそに、晴海達の荷物をひったくりクリスは蓼島の元へ走っていってしまう。
それにつられるように晴海も夏姫も走り出した。
エピローグ2:
トライデントに戻る前夜。海凰の甲板上では雅美と世良がいた。
「そろそろ、答え聞かせてくれるかい?」
世良の告白に『考える』といった手前、考えを言わなければならない。
雅美自身、考えていなかったわけではない。
「あのね」
「うん」
「私、特待生でしょ?」
夕闇に染まり、ライトだけがともる甲板上では、役者は二人だけしかいない。
「僕のこと嫌い?」
「きらいじゃない、ケド」
「やっぱ、ダメか」
「違うの、特待生になる条項のなかにね。就学中の恋愛は一切不可っていう決まりがあるの」
「なんだそりゃ」
事実だ。
勉強だけに従事するために作られた、つまらない約款の一つであったが。
「私は特待生やっていきたいし、でも世良のお兄ちゃんが好きなのは本当」
「じゃあ、卒業まで待ってればいいのかな」
「そうなっちゃうね」
「じゃあ、今のウチにツバつけとこう」
「あはは」
照れ笑いをする雅美の顎をそっと持ち上げ。
唇を重ねる。
「……!」
「ツバつっけたっと」
世良の顔が自分の目の前から離れたとき、雅美は少しパニックになっていた。
「え、もしかして。キスした?」
「したよ、だから雅美ちゃんはもう……オレのもんね」
「あ、あの」
上目遣いに雅美が世良に尋ねる。
「うん?」
「もう一回、つばつけてもらっても……いい?」
エピローグ3:
この大きな人工島での話はこれで終わる。
僅か二年の間に、数百年に一回という嵐よりも大きな嵐をこの島は体験した。
しかし、まだこれが終わりではない。
地球に人がいる限り、それは脈々と続いていく。
人と地球との関係。
この物語にはきっと、
……終わりはない。
To be Continued ,A Blade of the Olympos R.