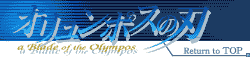シーン0:
ロス=ジャルディン島の遺跡が海中に沈み、あれから世界中で大変な事が起きていた。多国籍企業、トライデントコーポレーションの問題もそうだった。
副社長が姿を消し、企業の責任が出資をしていた日本・アメリカ、そして統括する国連にまで及んだ。内閣は総辞職、アメリカでは現大統領がリコールの嵐にさらされている。
トライデントUNはもとより、CH、REの計画も一時凍結された。
トライデントCo.社長である王社長は全世界に向けた放送の中で、副社長の独走と自分の管理不行き届きの責任を取り社長職を辞職した。後任人事についてはまだ決まっていない。
世界がどんなに動こうと、国際海洋大学の動きは止まらない。
トラコの資金援助を受けたとはいえ、独立採算性を取り、学校法人化していた国際海洋大学はトラコ傘下とは切り離され、解体構想からは外された。唯一有った事と言えば、副社長派に荷担したと言われた遠野秋桜とスセリ・シンクレアは自らの意志で荷担したと見なされたが、教授会の新たな座長となった菱垣達の弁護があり、またスセリは未成年であることから、秋桜に停学八週間、今年度分の単位没収と280時間の奉仕活動、スセリには停学2週間と48時間の奉仕活動の処分が決まった。
とはいえ資金基盤を失ったUN大学も今後の運営をどうするか、頭の痛い問題が山積みとなっていた。
そして、その全てが乗っている人工島自体は、遺跡の壊滅でトライデントUNを支える支柱も沈んだが、もともとフローティングブロック方式のUNにはさほど被害が無かったのが救いだった。今現在ではプリンセスホテル他日本防衛海軍と米軍が、占領の際に残った傷跡の復興に全力を注いでいる状況だ。
シーン1-1:
遺跡崩壊から2週間の時間が経った。トライデントUN国際海洋大学所属、海洋調査実験船『海凰』の再巡航式が行われた。
もともと海凰はアッパータイプの砕氷船でもある。アンノ君との激突で生じた船体全体の歪みが想像よりも大きく、40層にもなる海凰の装甲板のうち約10層が貫通し、半数にあたる20層に歪みが認められた為、8ヶ月以上の修理を余儀なくされた。
『……以上の祝典を終え、我々の復興のシンボルとして海凰はこれより、新たに第一歩を踏み出すのであり……』
船長の環太平洋(たまき・ひろし)の出発前の挨拶が終わり、海凰はゆるゆるとタグボートに引かれ岸壁を離れ始めた。
最初の寄港地である中ノ鳥島で補給を行い、夜に岸壁を離れた。
夜間航行の実験のためである。
「よし、菱くん、世良くん。そろそろ休憩に入ってくれ」
あまり広いとは言えない海凰の艦橋。
夜間航行の場合、プログラムまかせに自動運転を行い管理人として1〜2名が待機する程度なのだが、レーダーだけに頼った夜間航行と、自動運転プログラムの確認のため、人がごった返している。
「あ、は〜い」
今回、海凰にのった学生は28人。
その中には以前この海凰に乗ったことのある生徒が二人いた。
その他の生徒が海凰に乗り込んだのも、今現在のトライデントUNへの不安というのもあるだろう。
「わ、綺麗だね」
「そうだな」
二人は海凰の窓から外を眺めた。
中ノ鳥島の街の光が、真っ暗な闇海の中に浮かび空の星に負けないほどの光彩を放っていた。
「出航後ちょうどこの時間だな」
あの時は夕方に出発し、朝に中ノ鳥島に到着する予定だった。
今回の時間は逆ではあったが、出航しこの時間にエマージェンシーコールが鳴った。その音がその後の1年間の開始の合図のだったように今から見れば思える。
「昨日、あの波形を再生してみたんだ」
雅美はポケットからアンノ君が激突する際に記録された、異常な過1/αを記録した紙を取り出した。
「これって、医務室が故障じゃないかって研究者みせた波形だな」
「うん」
雅美はそれを人為的に過1/α波として再構成し読みとった。
「アンノ君はね、寝てたんだ。どうしてあんなに遠くに移動しちゃったのか自分でもわからなくて、自分が守るべき人、エテルナを探してた。エテルナとアンノ君は過1/αでお互いに居場所が分かり合えたの」
「でも、その過1/αに近い音源が多かった」
「そう、ブラウン運動板がアンノ君を混乱させた。でも徐々に本来の居場所であるトライデントに近づいてきたときに、エテルナに会えた」
「海凰にのったジェレミー先生か」
雅美は静かに頷いた。
「アンノ君はエテルナが船に閉じこめられてるって思った、だから助けるために船に体当たりした。でもジェレミー先生は怒ったんだと思う、アンノ君は船を壊そうとして助けだそうとしたのにジェレミー先生は船が壊れることを望まなかった。だから二度目の体当たりは回避された、アンノ君はそうして再び深海に消えたの」
「じゃあ教授会の連中は、あのアンノ君をどうしたかったんだろう」
世良の疑問はとても単純なものだった。
ジェレミーを海凰に乗せたのは教授会の決定である、ひいてはその教授会を操っていたのは副社長。副社長は海凰にアンノ君を引きつけさせてどうしたかったのか。
「推測でしかないけど、エテルナとアンノ君を会わせたくなかったのかも」
「でも、そうすると、だったら海凰は逆に引きつけたんじゃないか?」
「そこまでは判らないけどね、副社長に聞けばわかったかもしれないけど……もういないし」
すでに沖ノ鳥島の明かりは見えなくなり、冷たくなった海風が頬をなでる。
「じゃあ、そろそろ部屋にもどるか」
「世良のお兄ちゃんは明日シフトなに?」
「シフトBだから午後からだな」
「残念〜、私はシフトCだからあえないね」
「そうか」
「じゃ、おやすみ」
女子学生用に用意されたブロックへ行くためのドアを雅美が開けたとき。
「雅美ちゃん、あのさ」
世良の声かけに雅美が振り向くとそこには視線をすこしだけ外した世良がいる。
「ん?」
世良は髪をかきあげながら、暗闇で表情はわかりにくいが照れながら。
そして真面目な口調で。
「僕たち、つきあってみないか?」
「考えてみるね」
即答だった。
シーン2-1:
寒梅船内。「もう交渉の余地はない、蓼島とは何も話さん!」
「……」
「まぁまぁ二人とも」
寒梅は日曜昼間だけあって、昨日の酒宴の後、片づけに来た蓼島とクリス、そして愛と克司の四人だけ。
船内の片づけも畳の雑巾掛けも終わり、お茶を飲んでいた時のことだった。
クリスが蓼島に話を切りだした。
たった一言。
『婿に来てくれ』
クリスにしてみれば、1年のつきあいになり、拉致されたときもその他の時も常に蓼島が側にいた。
蓼島もしかり、だ。
しかし、クリスの言葉に蓼島が二の足を踏んだのが事の発端だった。
具合の悪いことにクリスは名門家督を継ぐ事が確定している、もちろん身分の違いとかいう問題ではない。
蓼島にしてみれば、もっと二人の時間をかけたかったのだ。
クリスが焦っている理由は蓼島にも判っている。
クリスは家督を継ぐ条件として、海洋大学での修学を望んだ。大学を出たら家督を継ぎ、分家筋あわせて数百人のキルシュシュタイン家をきりもりしなければならない。
蓼島にしてみれば、いきなりそんな家に婿に入れと言われても即答で返せるようなものではない。
「クリスは性急すぎるんだ、今コクられて『ハイ』なんて即答できるような問題じゃないだろ、だからもっと話し合って決めたいんだ、時間だってまだあと五年もあるじゃないか」
「5年しかないんだ、判らないのか?」
男女の別れる最大の原因が価値観の違いとはよく言った物で。
二人の間に入ってなだめている愛も、結局は静観するしかなくなった。
徳重は何も言葉を挟まず、ただ渋茶をすすっているだけだった。
「もう、判った。蓼島、お前はもう私の家族ではない」
クリスはそのまま立ち上がると、寒梅を降りていった。
「ちょ、ちょっと待ってクリスさん!」
愛はクリスの後を追う。
蓼島はクリスが船を降りた直後、渋い表情から少しばかり後悔を滲ませた。
「だったら、追いかけて謝るか、謝るのを待つしかないだろう」
「どっちも無理そうですけどね」
「まぁ、そうだな。それができりゃ最初から喧嘩なんかしないか」
クリスを追いかけていた愛が追いついたのは港をでた直後だった。
「ねね、やっぱりゆっくり話し合うべきだと思うんだけど、夫帯者としての意見として。やっぱねお互い夫婦になっても他人なのよ、結婚してもお互いの知らなかった面が見えるときもあるし、やっぱりもうちょっと時間をかけて……」
「……おばあさまが亡くなったんだ」
「え?」
「私の家は古い家柄なのは知ってるだろう? いまこの現代にありながらまだ古い考えがこびりついてる、私にもだ。誇りには思っている、でも少し煩わしくなってこの大学に来たんだ。せめて自分の永い人生、6年ばかり寄り道させてもらってもいいじゃないかって」
クリスが空を見上げた。
「今の家長はおばあさまだった、すべてを考え決断するのは家長の役目で、キルシュシュタイン家の人間にとってその決定は絶対なんだ」
「うん……」
「そのおばあさまが、最後に次の家長に私を指名した」
「……!」
「そう、もう大学にはいられないんだ」
「そんな……、いつ?」
「明日、家長不在では家が回らないからな」
ちょっと自嘲を含みながらクリスは微笑んだ。
「蓼島くんはその事」
「蓼島と私は……関係なくなった」
「違うとおもうよ、それ。なんか変だよ」
「蓼島と家を秤に掛けること自体がナンセンスなんだけどな、判ってるよ愛。まぁたった1年だったけど貴重な体験をしてきたし、もうここには心残りはない」
「違うよ、天秤にかけるのはクリスと家。クリス自身がどうしたいのか、ちゃんと考えなきゃダメ」
「蓼島は大切な人だよ、多分それは変わらない。でも家には私をまってる大勢の人間が居る、ちょっと野心家だが私の本当の妹を始め大勢の人間が」
愛には、空を見上げるクリスの姿が、この1年間の思い出を振り返るという姿より、涙がこぼれないようにしている姿に見えた。
「キルシュシュタイン家の理念は弱者を守る盾であり矛であることだ、そして開祖レオノーレ・キルシュシュタインの血は私に流れている」
クリスは悲しそうに言葉を続けた。
「きっと私の中の血を全部抜いてもな」
クリスは最後にそう言い残して港を出ていった、その悲痛な覚悟に愛はそれ以上クリスをつなぎ止めることは出来なかった。
愛の足が動く。
蓼島にこの事を伝えなければならない。
しかし、一足遅かった。
「ああ、やっこさんなら小型艇で帰っていったぞ」
「徳重さん、私どうしよう」
愛の話しに徳重は途中、何も口を挟まず黙って聞いていた。
シーン3-1:
「いいんですか、まだ謹慎中でしょうに」杉崎 終にはガイヤの声のメンバーとして、そして大学職員としての二つの面がある。
今回の騒動を見治めたあとは退職する予定だった。
そんな彼の目の前にいるのは、停学処分中のスセリ・シンクレア。
そしてスセリは彼が大学に残る事を決めた要因の一つだった。
「停学なだけで謹慎ではないですから」
いるのは杉崎の住んでいる大学職員用のマンションである。
日曜日の昼過ぎに普段ならない杉崎の部屋のチャイムが鳴った。
ドアを開けるとそこにいたのがスセリだった具合だ。
「なるほど」
「お邪魔します」
「どうぞ、汚してるけど」
そう言ってもこざっぱりと片づけられた部屋は杉崎の性格がよく出ている。
あまり大きいと言えないリビングに通されたスセリはソファに座り、辺りを見渡した。
そして一番目立つテレビの上にある写真立てに、一人の女性の写真が優しそうに微笑んでいる。線が細い女性の写真。
「あの写真、奥さんですか?」
「ああ」
紅茶をカップに注ぎ、持ってきた杉崎も嬉しそうに答える。
「綺麗でしょ?」
杉崎の何気ない一言がスセリにすこし突き刺さる。
「先生の奥様はいまどちらに?」
「どこなんでしょうか」
それは決してちゃかしたりごまかしたりする口調とは違っていた。
「え?」
「ボクの奥さんは結婚する前に死んでしまいました、親同士が勝手にきめた結婚だったので直接会ったことは何回もありません。メールのやりとりくらいだったかな、あと電話と。病気がちでなかなか外に出ることも出来ませんでしたし。彼女が死んだ後、親同士でまた勝手に結婚を白紙にしようとしたんです、反骨精神だったのかもしれませんが、私は彼女が死ぬ直前まで生きる希望にしていた事をかなえてあげることにしました」
「死後結婚ですか?」
「ええ、だからボクの奥さんは天国にいます。夫婦としてすごした期間はありませんが」
紅茶が少し揺れる。
「すみませんねぇ、自分だけおしゃべりが過ぎました。で、スセリさんが今日ここに来たのはどんな要件ですか?」
「奥様に……」
写真に視線を移す。
「宣戦布告です」
「え?」
「今日はお邪魔しました、また来ます」
スセリはそれだけ言うと荷物をまとめて玄関を飛び出した。
慌てていたのは杉崎よりも、スセリの方だった。
なんであんなセリフが自分の口から出たのか。
しかし、すでに喉から出た声は再び飲み込むことは出来ない。
「……死んだ人に、かなうはずはないか……な……」
職員寮から数百メートル離れた商店街の入り口まできて改めて思い返す。
死んだ人間の思い出は、よほどの悪名がないかぎり美化されることはあっても悪くなることはない。
それどころかさらに『いい人』として生身の人間には太刀打ちできない相手となる。
スセリは自分がこの大学に来たときよりも、ずいぶん変わった自分にため息をつく。
人を好きになるということは、ただ好きなだけではなんともならない事を。
本来ならもっと若年で得られるはずの感情を、スセリが得たのはついこの間の事だった。
深い思考をしない年齢ならまだよかった、しかしスセリは頭の中で色々な事を思いめぐらしてしまう。うその中身は上手くいくことよりも、駄目になってしまっているシミュレーションの方が遙かに多い。
スセリはため息を一つ、雨の降りそうな空に解き放った。
シーン4-1:
「だからなんでこんな事に巻き込まれるかしら?」「そんなのわたしがききたいですっ!」
ロス=ジャルディン島の有った場所。
「すみません、私が連れてきてしまったみたいで」
滝 智己と宵闇浮月がボートに飛び乗る。
「なんで、ぎょうさんお客連れてきてん?」
「私は遺跡の再調査にきただけですよ」
と浮月。
「わたしも」
と智己。
「ちょっとわけあって、親元から逃げてきました」
とあまりにも似合いすぎる白いワンピースと白い帽子に白いサンダルを身につけた少女。
「アンタが原因なんか?」
海藤瑠璃は操舵輪を思い切り廻しながら毒づいた。
「きっとまた本土に戻そうなんて考えてるお父様の追っ手かと」
「なんや多いなぁ、私の周りの人間ってこんなん」
瑠璃たち四人が乗った小型の船が逃げる。
それを四隻の船が追いかける。
「もう、あんな大騒ぎのあとだからしばらくは平和だと思ったのに」
智己のぼやきをみんなは聞き流す。
船速自体は同じ様だ、さっきから付かず離れずの距離を保っている。
「そういえば、あなたのお名前は?」
浮月は洋服のあちこちから使えそうな武器を探していた。
「海洋文化コースの藤原皐月と申します」
「こっちが瑠璃でこっちが智己で私は浮月」
もとよりゆっくりと挨拶している暇なんぞない。
浮月は揺れる船の上でゴソゴソと何かを作り始めていた。
「あら、コルトガバメント。ずいぶん古い銃をお持ちなんですね」
浮月は少し驚いたが手の動きだけは止まっていない。
「皐月さんって、普通のお嬢様じゃないでですね?」
「多分そうですね」
「普通ならバラバラの銃の部品見て、判るはずないもんね」
「あのさ〜、なんで銃なんか持ち歩いてるのよ」
智己の疑問は非常にもっともな物だった。
「この前見たいな事があったら大変じゃない、それにトラコが無くなったってことはここら辺を警備していた警備部ももう居ないって事ですし、まぁ念の為だったんですけど」
納得できそうで出来ない智己をしりめに浮月が銃を構えて狙いを付けた。
瑠璃の方は操舵で手一杯の状況、後ろをみている余裕もない。
パンパン!
コルトガバメントが火を噴く。
しかし追っ手の船の操舵室の窓を割っただけで速度は変わらない。
ズドドドドド!
追っ手の船から機関銃が放たれた。
「アサルトライフルかしらね、良く持ち込めたものです」
皐月は相変わらずの口調である。
「なんで落ち着いていられるのよ、ここは日本よ戦争反対〜」
智己は泣く寸前だった。
「ということは、多分、お父様の追っ手では無いようですね」
「てめぇらきたねぇぞ! 素手で闘え素手で!!」
瑠璃の叫びに返ってきたのは機関銃の弾だった。
「先に撃ったのは私たちの方だと智己はおもう」
そうして数分が経った頃だった。
追ってきていた船が一斉にきっさきを返して行く。
『こちらは日本防衛海軍です、この水域は進入禁止になっています直ちに水域外へ出なさい』
「あ、はい。かしこまりました」
皐月が立ち上がりペコリと頭を下げる。
浮月は死角になっている場所から銃を海の中へ投げ捨てた。
智己は一気の緊張からの開放で少し惚けていた。
(せやったら、あのヘンな奴らはいったいなんだったんや? 何故、うちらを追いかけ回した。しかもあんなアブナイ武器を持って。なんかまたヤバイことになりそうやなぁ)。
瑠璃は追っ手の船がいないことを確認しながら海洋大学の港、フォローウィンドへ舵を取った。
港に着いたときに瑠璃は一つの疑問を投げかけた。
「なぁ、あんたらの中でだれか、あいつらの姿みたやつはおらん?」
シーン5-1:
「こったん! こったん!!」「うん?」
第4大講堂。
「ふぁぁ〜」
オオアクビを人が少なくなったとはいえ人の前で恥じることなくやってしまう女と、それを見て呆れてる女。
「こったんってなに?」
「私がつけた詩絵羅のあだ名」
「あ、そ」
日本とアメリカのハーフの虎杖詩絵羅。
「で、なんで『こったん』?」
「イタドリって呼びにくいから『こづえ』うんでもって『こったん』」
「ああ、なるほどね」
「そう言いながらまた寝ない、あんたの会社に行くよ」
詩絵羅が社長を務めるドルフィン便は小型郵便の搬送の会社である。
現代におけるバイク便の様な物だと考えればいい。
トライデントUNに同業者がいないこと、そして2051年現在も大事な契約はデジタル上ではなく紙契約であることがこの仕事を成り立たせている。もちろん料金を払えば学生の忘れ物を届けに行くこともするし、違法行為でなければ仕事はなんでも引き受ける。
「香津美は急ぎすぎだ」
「あ〜もう本当に寝起きは駄目人間だね」
詩絵羅の腕を掴み上げる香津美。
ドルフィン便は事務所を爆破された後、社員共々離ればなれになってしまった。
そして事務所を失っては営業ができず休業状態であったが、先日ようやく壊された事務所の保険金が降り前の事務所よりやや大きめの、大通りに面した場所に新事務所を構えることが出来た。
ポツポツといままでドルフィン便にいたメンバーも戻り始め、ようやくではあるが営業再開とあいなった。
「夏川は西地区の長谷さんとこから荷物引き取ってそのまま南地区で荷物を受け取り、流風は夏川からその荷物もって大学の吉川研究室に」
『夏川了解』
『早瀬りょうか〜い』
事務所では一人の電話番兼オペレーターをしていた叶野水月除いてだれもいない状態だった。
「おはよう」
「おはようございます」
「おはよう」
「社長、こっちが電気屋さんの請求書、こっちがチラシの印刷代」
「ほい、ありがと。じゃあ幹も配達に入って香津美もよろしく」
午後4時、郵便会社が営業を終了するこの時間帯からにわかにドルフィン便が忙しくなる。
トライデントUN南住宅地区。
3分ほど早く合流した夏川幹と早瀬流風は少しだけ休憩を取っていた。
「あのさ、うちの社長ってなんでこんなに仕事いれるのかな」
「儲けたいからじゃない」
「儲けるったってまだ僕ら学生だよ」
「だったらこんなとこで聞くより、直接社長に聞いてみたら?」
スポーツドリンクをショルダータックから外して流風が呟く。
「まぁそうなんだけどさ」
学生であれば奨学金を得る方法はいくらでもある。
卒業後の進路は狭くなるが、1円も1セントも出さずに卒業することだって可能なのだ。
中には返済義務のない国の奨学金だってある。
アルバイトをするのは少しばかり自分の自由になるお金が欲しいときだけなのだ。
そう、普通ならアルバイト程度でいいのに、なぜ社長は会社を作ってまでお金を儲けようとするのか。
夏川が考えていたとき、ビジフォンが鳴った。
どうやらまた新しい仕事の様だ。
その日の夜。
ドルフィン便も夜勤者を残して閉店となった。
虎杖は社員全員に日当を手渡すと、受け取った領収書を鍵付き金庫に閉まって勝手口から店を出る。
歩く先は学生寮ではなく逆の方だった。
トライデントUN中央病院。
「ってわけで、そんな尾行じゃ判ってくださいっていうもんだ」
詩絵羅の声に、諦め顔で出てきたのは夏川ではなく、流風の方だった。
「社長は社員の事、よーくわかってるのに社員が社長の事を知らないのは不公平でしょ」
「あたしは誰にも隠し事なんかしてないよ、みんなが聞いてこないだけでさ」
「ふ〜ん、じゃあここに何の用事で来たか、教えて貰えるの?」
詩絵羅はちょっと苦い顔をしてタバコをもみ消し、何も言わず病院の中へ入っていく。
口にはしていないが、ついて来いの意味に流風は受け取る事にした。
深夜とはいえ廊下の電気は明るく、行き交う専門看護師と医師。この時代、治療は医師との契約である。病院も医師に場所を提供しているだけである。さながら診療所が集まった医療のデパートだ。
「お世話になってます」
「いえ、ヒロくんならさっきから眠ってますよ」
葛城 操と書かれた名札兼IDカードのバッチを着けた看護婦が先導して、外科病棟の個室前に立ち止まり、そのIDカードを読みとり機に滑らす。ドアの鍵の開く音がしてから、詩絵羅は静かに中に入っていく。
「紹介するよ流風、あたしの弟で虎杖ヒロシ」
流風はベッドの上に着けられた名札、そして血液型など書かれた札を見た。
十一歳。
というには小さすぎる気がする。
点滴が輸液ポンプに繋がれ、定期的にそして正確にブドウ糖を滴下していく。
「詩絵羅ねえちゃん?」
ベッドに寝ていたヒロが目を覚ます。
「ああ、で後ろにいるのがお姉ちゃんの友達で早瀬流風っていうんだ」
「こんばんわ、虎杖ヒロシです。姉がお世話になってます」
年齢にそぐわない挨拶に流風が少し面食らう。
詩絵羅がヒロの頭を撫でてるとき、その表情は普段なら見れない、想像しづらい優しい物だった。
20分ほどの面会が終わった後、詩絵羅が向かったのは医事科だった。
「はい、本日の入院費精算ですね。合計8545円になります」
流風は我が耳をちょっと疑った。
本日の清算ということは一日で8545円なのだ。
これが1ヶ月30日となれば約26万円。
帰り道、詩絵羅の方から話題を切り出した。
「あたしとヒロは、異父兄弟ってやつでね。アメリカで母親が出ていった後に日本で再婚して出来たのがヒロなんだ。でも、再婚相手の旦那が最低なヤツでね。ヒロは虐待されて母親は逃げだし父親も失踪、一人で8年も施設にいたんだ。あたしのほうも父親が死んで、でもある程度のお金は残して置いてくれたからなんとかなったんだけど。ヒロの噂を聞いて日本で見つけたとき、ヒロは本当に非道かったんだ。産まれながらにして神経障害を持っていたヒロは施設でも虐待されていた。だから私が引き取った、アメリカで裁判起こして権利をこっちの物にした。でもヒロは施設で保険に入ってなかった、保険料は日本政府から福祉費用として施設に入っていたのにピンハネしてたんだよ」
保険制度が崩壊しているこの時代に、民間の保険に入れない人々は莫大な治療費を自費でまかなわなければならない。
詩絵羅がタバコに火をつけ、紫煙を吐き出す。
「ヒロの病気はまだ病気じゃなくてね」
「なんで?」
「まだ難病指定もされてない新しい病気なんだ」
それは民間の保険会社に後から入ったとしても、治療費が払われない事を意味していた。
「その新しい病気を研究している医者が、日本人じゃこのオリポにしかいないって聞いてね」
「……で、海洋大学に?」
「この島に住むには、生徒かトラコ職員の家族じゃなきゃ駄目だろう? だから必死で勉強したさ」
詩絵羅にとって、海洋大学は目的ではなく手段だった。
「ヒロにアメリカ人の市民権の取得は時間がかかりすぎるし」
「それで始めたのがドルフィン便?」
先にも述べたとおり、大学に通って卒業するだけなら一円もかからない。
アルバイトする学生は、仕送られる生活費の他、ほんの少し自分の自由になるお金が欲しいときにだけバイトするのが常識である。だから自ら会社を作ろうとする学生なんかいやしない。
「そうだな、自分に出来そうなことを考えてたらそうなった」
「なるほどね」
「すまないけど、流風。この事はまだちょっと……隠し事は無しとか言った手前なんだけど」
「いいわよ、誰に頼まれた訳で無し」
「サンクス、明後日にヒロが大きな手術をするんだ。その日は私が会社を休むからその時はみんなに事情を説明するつもり」
「……良くなるといいね」
「ああ、早くヒロにドルフィン便を見せてやりたいね」
潮を含んだ風が空を流れる。
最初は不慣れだったこの風も、いつのまにか何も考えず受け入れられるようになってきた。
シーン6:
「ファーストコンタクトは成功したようだな」「はい、日本防衛海軍がこなければ大成功だったんですが」
「そこまでまだ結果を求めていない、奴らの武器を使ってこちらの武器にするのが目的だからな」
「自らの三つ又の矛にとどめをさされる海王ですか」
「さしずめ、我々はゼウスか」
「いいですねそれ」
「神々の島を活かすも殺すも我々ゼウス、全てがガイアへの愛だよ」
「ではセカンドレベルの計画を開始します」
「ああ、あと二日だ。我らがガイアを大自然を、破壊する悪しき科学者の温床を滅する日までな」
シーン7-1:
遠野秋桜。とおの・あきお、と読む。
自分と恋人である桝家春海との部屋中でひとりベッドに横になっていた。
「秋桜さん、朝ご飯できたよ」
「ありがとう」
事件が終わって以来、ずっとこうだった。
一週間に3回、8時間の奉仕活動以外の用事で部屋を出ることもなかった。
「あのさ、はるちゃん」
「なに?」
「髪の毛切ってくれる?」
「いいよ」
秋桜は海洋大学では珍しい超ロングヘアだった。
手入れが大変で、今までも毛先を整える位なら春海がやっていたが、今日は少し趣旨が違っていた。
「いいの?」
「うん、おもいっきり」
春海が秋桜の襟首あたりから鋏を入れる。
それまで腰まであった栗色の髪が床に敷いた新聞紙の上に落ちていく。
鋏が入れられる、髪の毛が落ちる音、一つ一つに聞き入っている様に見える。
「はるちゃん、そのまま話し聞いてくれる?」
「うん」
「私ね」
「まだ、言いづらいなら話さなくていいよ」
「大丈夫……、私ね本当は御陵の娘なんだ」
御陵、トラコの副社長であった男で今回の事件の首謀者だった。
「そう」
「娘というのかな、私はあの御陵の遺伝子から産まれたクローンなの」