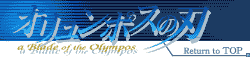シーン0:
トライデントUN第三期工事現場。建設資材が乱雑に積み上げられた迷路のようなこの場所に、一隻の小型艇が流れ着いていた。C-3型連絡艇。トライデントUNの緊急脱出艇として各ブロックに装備されているタイプの船だ。
「……ん、んぅ」
建設資材の間から漏れ落ちる朝の光を浴びて、小型艇の中で寝ていた宮前五郎(みやまえ・ごろう)が目覚めた。
体を起こすと、まわりを見回す。
昨日隣にいた少女の姿は、そこにはなかった。
「あいつ、行ったのか――」
トライデントCo警備部より脱出した五郎と少女――山瀬摩耶(やませ・まや)は、小型艇の中で今後の身の振り方を話し合った。そこで五郎は『ガイアの声』の保護下に、摩耶は地下に潜伏することに決めたのである。
「これがボクの命綱か……」
ポケットの中に手を入れると、データカードの固い感触が伝わってくる。
五郎はそれを確かめると、立ち上がった。
「行ってみるか。『ガイアの声』のところに」
シーン1:
トライデントUN小暮研究室。環境保護団体『ガイアの声』の実質的な活動拠点でもあるこの研究室に、海藤瑠璃(かいとう・るり)はいた。
「全く、レポートなんてやってられへんわ」
ホロペーパーに何かを書き込み、また消す作業を何度も繰り返しながら、瑠璃はぼやいていた。
「明日までに20KBなんて、小論文の枠をはみ出ているで――。全くコリーンの奴、人を殺す気かいな」
意外かもしれないが、瑠璃はトライデントUNの授業を真面目に受けていた。彼女はトライデントUNの開発には反対だが、大学自体には特に何も思っていないのである。
「あまりはかどっていないようだね」
研究室の主である小暮教授が、温厚そうな笑みを浮かべながら、瑠璃に話し掛けた。
「あ、センセ。ほんまやってらませんよ。文献もキチンと精査しなあかんし、もー、時間があらへん――」
「勉強で忙しいところ悪いが、瑠璃君にお客さんだよ」
「お客さん?」
「はじめまして」
頭に古ぼけたゴーグルをつけた男が、瑠璃の前に立っていた。
「ボクは宮前五郎。警備部の間瀬という人から、あなたにこれを渡すように言われてきました」
五郎はポケットの中から一枚のデータカードを取り出すと、瑠璃に見せた。
「これはなんや?」
「それは見てもらえれば分かります」
もしも瑠璃が何も知らなければ、自分の話は誇大妄想狂と思われて追い出されるのが落ちだ。そう思った五郎は、慎重に言葉を選ぼうとする。
「なんや怪しいなぁ。センセ、間瀬って言う人知ってます?」
「間瀬くんがどうしたって?」
「センセ、知ってるの?」
胡散臭げにデータカードを見ていた瑠璃は、慌てて姿勢を正した。
「ああ、間瀬くんは我々の協力者なんだよ。立場が立場なので、あまり大っぴらに出来るものでもないけどね」
「このデータカードの中の情報を、瑠璃さんに渡すように言われたんです」
こでまでの事情をかいつまんで話す五郎。
「――と言うわけで、危うく自治警察送りになるところを逃げてきたんです」
「ごっつい話やな」
思わずため息をつく瑠璃。
「で、そのデータカードの中に、うちらに見せたいものが入っていると」
五郎は黙ってうなづいた。
「ほなら、取りあえずそれを見てみよか。詳しい話はそれからで構わへんやろ。浮月さん、このデータカードを読むのって、どこかあります?」
最近瑠璃の周りに集まっている学生の中の一人、宵闇浮月(よいやみ・ふづき)を瑠璃は呼び止めた。
「そこのMASSが空いてますよ。ですが、その中にまさかMVウィルスとか入っていませんよね?」
「MVは入っているけど、あれが医療系のホストを破壊するウィルスだというのは、トラコ側の流したダミー情報だよ」
五郎が答える。だが浮月は首を振ると、
「確証が取れません。もしも何かあってからでは遅いですから……」
「なんかいい方法でもあるんかいな?」
浮月は小首を傾げると、
「ネットワークに繋がっていないマシンならば、万が一の場合でも大丈夫なのですが」
「それならば、これを使えばいい」
同じく学生の八ヶ岳恵美(やつがたけ・えみ)が取り出してきたのは、昔懐かしいタブレットPCだった。
「ネットワーク機能は壊れているので大丈夫だ」
「これはまた骨董品だな」
呆れたようにつぶやく五郎。
「どう、使えそう?」
タブレットPCを起動し、設定を確認していた浮月に瑠璃が尋ねる。
「OSにWAVEが入っていますし、大丈夫、行けます」
「OK、それじゃあのぞいてみましょか」
---
MVについての記録(Vol1)
1-1:MVについて
形態:80nm・多角性不定形
活動温度:36度から39度
DNA・RNA分離:未分離
1-2:感染経路
接触感染(血液媒介)、経口感染(汚染肉・汚染血の直接摂取)
1-3:培養
寒天培地:不可
血液培地:不可
コンソメ培地:不可
嫌気培地:不可
硫黄培地:不可
細胞培地:不可
1-4:増殖性
特異的な繁殖を示す。
体内のみでの繁殖であるが、ある範囲内に一定数の同族が存在すると分裂・増殖が行われなくなり、また不活化する。
---
「なんやこれは?」
「何かの実験レポートみたいですね」
浮月はペンを動かし、画面をスクロールさせる。
---
3-1:動物投与実験A
100匹のラットにAの血液を直接経口から摂取。
10分以内に死亡:100%
3-2:動物投与実験B
18匹の無作為選択ほ乳類にAの血液を直接経口から摂取。
10分以内に死亡:16例
30分以内に死亡: 1例
3時間後処分 : 1例
---
「ここから先は、データの破損が激しくて読めませんね」
記号の羅列を見ながら、浮月が告げた。
「ざっと見た感じ、この中に入っているデータが本物ならば、トライデントCoは何らかのウィルスを使って人為的に細胞をガン化させる実験を行っていたみたいですね」
「ガン化して一体、どうするつもりなんだろう?」
「生物兵器とかちゃうやろな」
瑠璃がさらりと危険な言葉を口走った。
「いや、それはないだろう。生物兵器の開発として利用するには感染力が低すぎるんじゃないか」
「確かにそやなぁ」
瑠璃は首をひねる。
「そういや、体中のガン細胞がガン化したら、一体どうなるんだろう?」
咲コーヘー(さき・-)は誰とはなしにつぶやいた。
「それは多分、こうなると思う」
五郎はポケットの中からもう一枚のデータカードを取り出すと、タブレットPCに入れた。
「――かなりショッキングな映像なので、覚悟してみてください」
タブレットPCに映し出されたのは、全身が悪性腫瘍(=ガン)に覆われた死体の姿であった。
思わず息を呑む一同。
「これは?」
 「3ヵ月ほど前に廃棄物処理場で発見された変死体です。全身がガン化し、急激な飢餓状態にあります。そしてここに記されたNo.11の文字が――」
「3ヵ月ほど前に廃棄物処理場で発見された変死体です。全身がガン化し、急激な飢餓状態にあります。そしてここに記されたNo.11の文字が――」「と、取りあえずその画像を閉じてくれへんか?」
目を背けながら、瑠璃が頼んだ。
「了解です」 画像が一度閉じられる。
「いろいろな情報を総合的に検討した結果ですが、トライデントCoはこのMVを用いて人体実験をしているものだと思われます。この変死体もその実験の結果かと――」
「人体実験――」
乾いた声が響く。
「ちょっと待ってください」浮月が疑義を唱えた。「このファイルが本物かどうか、確かめないと」
「ボクはこのファイルのために、危険な目にあったんだよ」
「まあまあ、ちょっと落ち着いて」
コーヘーが間に入る。
「確かに突拍子のない話だし、いきなり信じろといわれても無理だと思うけど――。どう思います、先生?」
「う〜ん」腕を組み考え込む小暮教授。「正直、分からん。ただ……」
「ただ?」
「ざっと見た限り、このデータの整合性はそれなりに取れている。いたずらにしては手が掛かりすぎだ。いかにここの連中がいたずら好きだとはいえ、ここまでやる奴はおらん」
「とすると、これを信じて動いた方がええって訳やな」
「うごくってどうするの〜?」
日向美也子(ひゅうが・みやこ)が手を上げた。
「正直、今すぐどうこうというのは思いつかへん」
瑠璃は手を伸ばすと、データカードを取り出した。
「このデータをそのままネットとかで流しても、カンパニー側の情報操作で流されてしまうだけや。何か決定的な――証拠みたいなんがあらへんと」
「変死体の検死結果とか?」
「それも一つの手やな。この写真をつければ、かなりの説得力があるやろ」
「間瀬さんの力を借りれば手に入るんじゃないか?」
五郎は尋ねた。警備部の人間ならば、検死結果位手に入れるのは簡単なはずだ。
「けど、あまりその人を当てにするのも問題があるんじゃない?」
「なんでや、恵美さん?」
「その間瀬って人、言ってみればガイアがトラコに送り込んだスパイみたいなもんじゃない。あんまり派手な行動をとらせて疑われたらおしまいよ」
「確かに……」
「ということは、出来るだけ自分たちでなんとかしよってことやな」
「そういうことになるわね」
「他に証拠になるようなものと言えば……」
「ねえねえ」美也子がコーヘーの袖を引っ張った。
「なんだい?」
「みゃーこ思うんだけど、人魚さんを探せばいいと思うの」
「人魚か――、確かにこのファイルも、マーメイドで検索してヒットしたものだし、何らかの関係があることは間違いないです」
MV……マーメイド・ヴィールス……マーメイド……人魚。
「探してみる価値はありますね」
「分かった。ほならうちらはあの人魚探しや」瑠璃は軽く手を叩くと、「明日から忙しくなるで。みんな手伝ってや」
シーン2:
それから三週間後――、瑠璃たちは洋上にいた。最初に人魚が目撃された実習海域を中心に扇型の捜索範囲を定め、それを丹念になぞっていく。高性能CCDカメラとパッシブソナーを駆使し、捜索範囲から小魚一匹泳ぎ出る隙間もない。
「――それでも見つからへんねんなぁ」舷側に捕まり、瑠璃はぼやいた。「全く、人魚さんはどこにおるねん」
「そういえば、この中で今までに人魚に会ったことがある人って、みゃーこと瑠璃だけなんだよね」
「うちは殆ど覚えてへんねんけどな。助けてくれた人の話やと、そうらしいわ」
「また会いたいなぁ。人魚さんに」
「ほんまや。はよ出てきて欲しいで」
瑠璃は首から掛けたペンダントに手をやった。それを見ていた浮月が尋ねる。
「そのペンダント、いつも首から掛けていますね」
「これ!?」
「なにか大事なものなんですか?」
「ま、まあね」瑠璃は慌ててペンダントから手を放す。「一応、両親の形見だし――」
「8年前の事故でお亡くなりになったそうですけど……」
「知ってたんかいな」瑠璃は舷側にもたれかかると、晴れ渡った冬空を見上げ、「そうや。今もこの海のどこかで眠っているはずや」
「ふ〜ん、そうなんだ」
「このペンダントはな、うちのおかんの家に代々伝わってきたもんらしい。元々は400年ぐらい前に、スペインから来た先祖が持っとったもんらしいけどな」
「スペイン?」
「詳しくはよう知らんけど、女だてらに私掠船の船長やってたらしいで」
瑠璃は目を細めると、子供のころの記憶をたどった。
子供のころに両親が語ってくれた遠い先祖の物語。帆船同士の砲戦や、カリブ海の黄金、闊歩する海賊たちが、瑠璃の心に海への憧れを育てたのだ。
「人は海から生まれ、海に生き、海に還る」
小説の一節を唱える瑠璃。
「瑠璃は海が好きなんだね〜」
「そうや」瑠璃は遠く水平線を見回すと、ぽつりと呟いた。「だから守りたいんやろな」
同時刻、小暮研究室。
「ちょっと尋ねたいんだけど――」咲コーヘーは、研究室の学生に話し掛けた。「あの海藤さんってどう思う?」
「どう思うって言われても」
「あ、いや、彼女ってかなり過激なことを言っているように思えるんだけど、ここの研究室ってみんな同じようなことを考えているのかなと思ってさ」
学生たちはほんの少しだけ考えると、
「別にボクは彼女と同じ考えをしている訳じゃないよ。一部賛成、一部反対ってところかな」
別の学生は、
「確かに言っていることは過激かもしれないけど、でもあの子、無茶なことはしないしね。本当にどうしようもない連中は、爆弾テロでも平気でやるし」
「なるほどね」
確かにこの間の事件でも、テロをやろうとしていた連中を体を張って止めたらしいし――。でも、それだったらなんで青江さんは叩かれたんだろう?
「彼女は評論家が嫌いなんだよ」首を傾げるコーヘーに、小暮教授が言った。
「評論家……ですか?」
「どうも君たちを見ていると思うのだが、君たちは一体彼女に何を求めているんだい?」
唐突な質問。
「海藤くんは『ガイアの声』のメンバーだし、あの外見と行動力だ、非常によく目立つ。だけど、彼女はその反面、16歳の女の子だ。
そんな彼女が叫ぶことに、君たちは『それは違う』『それは間違っている』としかい言っていない様に思えるのだが、気のせいかい?」
「そういう人たちばかりではないと思いますが――」
「ならばいいんだけどね」
小暮教授はコーヘーの肩に手を置くと、
「彼女のことをよろしく頼むよ。ただ……、自分が本当にやりたいことがあるのなら、そちらをやってくれよな」
シーン3:
再び一週間が過ぎた。相変わらず人魚の気配はどこにもなく、捜索班の士気は最初の半分以下にまで落ち込んでいた。
「捜索個所を変えてみよか」
船橋で海図とにらめっこしていた瑠璃は、
「03セクターから06セクターまで、海洋牧場の方をメインに置いてみよ」
「了解」
舵輪を持つ片桐詠二(かたぎり・えいじ)が、大きくそれを回す。
大きく傾きながら、船は進行方向を変えた。
「なになに、針路変更したの〜」
キャビンで寝ていた美也子が姿をあらわした。
「ええ加減、手がかりもないしな。ちょっと気分を変えて、海洋牧場の方を探してみようと思うねん」
「人魚さんもご飯食べるしね〜」
「そうやね」
美也子のとぼけた言葉に、瑠璃の顔に久しぶりの笑みが浮かんだ。
「あいつを危険な目に遭わせれば、きっと人魚が出てくるはず……」
瀬名しぶき(せな・―)は、瑠璃が海に出てくるのを虎視眈々と狙っていた。
ホーリットと共に跳躍し、船に乗っている瑠璃を海中に引きずり込む。そうすれば前回と同じように、人魚が瑠璃を助けにくる。
「あいつと人魚を会わせてやるんだ――」
しぶきは瑠璃の真っ直ぐな姿勢に憧れていた。だから彼女のために何かをしてあげたい。そう純粋に思っていた。例えそれが、歪んだ愛情に近かったとしても――。
そしてその機会は訪れた。
「あれだね。あいつの乗っている船は」
遠目に一隻のクルーザーが見える。その前甲板に特徴ある蒼い髪が見えた。
クルーザーは速度を落とすと、ゆっくりと海洋牧場に沿って進んでいく。
「ホーリット、行こう!」
しぶきは海面に身を躍らせた。
クルーザーの舳先に立ち、水面を見つめている瑠璃を、柏木竜一(かしわぎ・りゅういち)は隙なく見張っていた。
数日前から警備部の間瀬課長をはじめ、宮前五郎や山瀬摩耶との連絡が取れなくなっていたのだ。彼らの共通点は一つ――MVに関する情報に接していたこと。となれば、次に襲われる危険が高いのは瑠璃をはじめとする我々だ。
ドルフィン便の事務所が突然爆発した事件もある。注意に越したことはない。
「巻き込まれた身だが、ここまで来たら最後まで付き合うしかないか……」
竜一が呟いたそのとき、左舷前方の海面から、一頭のイルカが飛び上がった。
「な、なに?」
一瞬、瑠璃から注意がそれる。
イルカは彼の目の前を通り過ぎると、
「きゃあ!」
蒼い髪が舳先から消えた。
そして次の瞬間、イルカは右舷の海面に飛び込む。
揺れるクルーザー。
「何があった!?」
竜一は舳先で呆然と座り込んでいる美也子の肩をゆすった。
「る……瑠璃が、瑠璃がしぶきにさらわれちゃった」
「なんだって?」
慌ててイルカを探す竜一。
「あそこだ!」
遠ざかっていくイルカの白い航跡。
竜一は振り向くと、詠二に叫んだ。
「取舵一杯。全速前進だ!!」
「あいよ」
ブラウン運動板と電磁推進を全開にしたクルーザーが、猛スピードでイルカを追い始める。
「海の中なら負けないぜ」
竜一は積んであった銛をつかむと、イルカをにらみつけた。
「げふげふげふ……」
「悪いけど、ちょっとだけ我慢してな」
腕の中でむせる瑠璃を見て、しぶきは口の中で呟いた。
「息が出来なくなったら、あたいかホーリットが助けてやるからさ」
「きゅぃきゅぃ」
元々人命救助のための訓練を受けているホーリットが、海面に上がろうとするのを抑えながら、しぶきは後ろを振り向いた。白いクルーザーの姿が見える。
「それにしても、しつこいな」
直線勝負ではクルーザーには勝てない。ならば――。
しぶきは海洋牧場に進路を向けた。集魚塔や定置網の張り巡らされたそこならば、クルーザーも追っては来れない。
シーン4:
『それ』は突然やってきた。『太平洋津波警報センターより緊急連絡。北太平洋上に突然波高4m前後の津波が発生!』
トライデントUN航路管制センターは、突然の警報にパニックに襲われた。コーヒーを飲んでいた主任管制官が慌ててヘッドセットをつかみ、当直のオペレーターを呼び出す。
「火山の噴火か何かか?」
「いえ。UNをはじめ、気象庁他の地震計には反応ありません」
『米太平洋軍司令部より緊急連絡。本島に向かって時速200ktで航行する潜水物体を発見。警戒を要する』
「200kt!? 米軍の連中も頭がおかしくなったのか?」
「データ解析中――」
「どうした?」
「データ確認、転送します」主任管制官のディスプレイに、一直線に伸びる航跡が映し出される。「間違いありません。潜水物体は存在します」
「まるで旧ロシアののシクヴァルみたいだな」
驚きを隠せないまま、主任管制官はディスプレイを見つめた。
「あと3分13秒後に、本島近海に到達します」
「津波警報を発令。海岸付近にいる連中を全員退避させろ。近くにいる船舶は、急いで波に正対しろと」
「了解」
トライデントUN中に津波警報が鳴り響く。そこかしこに設けられた水密シャッターが次々と閉じていく。
「津波警報だって?」
海洋牧場の中をちょこまかと逃げるイルカを追いかけていたクルーザーにも、津波警報の発令は届いた。
「あ、あれ!」
美也子が水平線の彼方を指差す。そこには白い波頭が見えた。
「近づいてくるぞ」
「くそっ」竜一は地団駄を踏むと、詠二に叫んだ。「取舵一杯!」
「な、なんだぁ?」
「あの先頭、何かいるよ?」
次の瞬間、海面が大きく盛り上がり、そして爆発した。
突発的に起こった大波に、クルーザーは木の葉のように揺さぶられる。
「――なんだあれは?」
ぶれる視界の中、詠二は『なにか』を目撃した。
「龍――」
水柱の中から現れたのは、『龍』のごとき生物だった。
いや、生物は生物でも"動物"ではない。詠二の見るところ、その表面は木で出来ている様だった。
『龍』は咆哮すると、瑠璃をさらったイルカに襲い掛かる。
水面が割れ、イルカと、その背に捕まっていた少女二人が宙を舞った。余波を受けて、海洋牧場の設備が次々と崩れていく。
「瑠璃、しぶき!」
美也子の叫び。
『龍』は一度海中に沈むと、再び浮上した。
その背中には瑠璃の姿が――。
「『海凰』が遭遇したのはあれなのか……」
唖然とする一同を尻目に、『龍』はゆっくりと体をうねらせ、クルーザーに近づいてきた。そしてクルーザーの横でピタリと止まる。
「……助けろって言ってるみたいだよ」
美也子は『龍』を見つめながら呟いた。
「あ、ああ」
生返事を返す詠二たち。
『龍』は催促するように吼える。
「早く、他の人が来ちゃうよ」
「分かった」
詠二たちは『龍』の背中に飛び乗ると、気絶している瑠璃をクルーザーに運んだ。
『龍』は静かに沈んでいく。
「行っちゃうぞ!」
「一体、なんなんだ、あれは……」
思い思いの感想を浮かべながら、『龍』を見送る一同。
遠くから警備部のボートが近づいて来るのが見えた。
シーン5:
「よくよく溺れるのが好きな奴だな――」クルーザーに乗り移ってきた御徒町たくや(おかちまち・―)は、開口一番言い放った。
「船に乗っていたのはこれで全員か?」
「ああ、そうだ」
警戒感をあらわにしつつ、竜一は答える。
「しぶきがいないよ」
「しぶき? それは誰だ?」
「みゃーこの友達。イルカと一緒にいたんだけど、あの津波で――」
「瑠璃をさらおうとしたんだ」
御徒町の目が細くなる。
「どういうことだ、海藤瑠璃?」
「どうもこうもあらへん。そのしぶきにいきなり海に引きずり込まれて、あとは見てのとおりや」
首筋のあざをさすりながら、瑠璃は答える。
「この間は瑠璃を助けてくれたに〜」
「ああ、あの娘か……」
「取りあえず、早く探さないと」
厳しい表情で詠二が告げる。
「そやな。見つけたらぎったんぎったんにしてやる」
十数分後、海洋牧場の構造材に閉じ込められ、身動きが取れなくなっていたイルカ(なんとトライデントUNが誇るホーリットであった)は発見された。だが、しぶきが見つかることはなかった。
そしてしぶきは、その日より姿を消した。
シーン6:
蒼い海の中を、しぶきは漂っていた。ゆらめきの中に明るい光が見える。
どこか安堵したような、不思議な感覚がしぶきの心を満たしていた。
(ああ、あたしはここで死ぬんだ――)
冷たく、そして暖かな手にしぶきは覆われる。
その感触を、しぶきは覚えていた。
(人魚……)
しぶきの意識は、闇の中へと落ちていった。